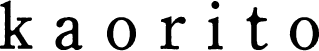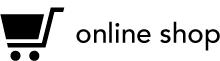「最近、和精油が気になっている」
「日本の香りに癒されるって、どんな感じなんだろう」
「アロマは好きだけど、海外のものとはどう違うの?」
——そんなふうに感じて、このページにたどり着いた方もいるかもしれません。
数年前まで、日本産の精油はそれほど注目されていませんでした。
「情報が少ない」「品質は大丈夫?」「どう使えばいいの?」
そんな声も少なくなかったのが正直なところです。
けれど今では、「和精油 人気」と検索されるほど、注目度は確実に高まっています。
なぜ今、「和精油の香り」が求められているのでしょうか。
その理由は、日本の精油が“ただの国産アロマ”ではなく、香りを通して文化や感性を映し出している存在だからだと、私たちは感じています。
目次
- 今、注目される“和精油人気ランキング”5選(かおりと編)
- 香りのやさしさと、暮らしへのなじみやすさ
- 日本人の感性に寄り添う「和の香り」
- 国産だからこその安心と信頼
- “自分だけ”の香りに出会えた、特別な感覚
- ナチュラルでシンプルなライフスタイル
- あなたも、「和精油を使う人」のひとりに
今、注目される“和精油人気ランキング”5選(かおりと編)
和精油人気の理由を語る前に、お客様の声やリピート率をもとに、「かおりと」で人気の高い精油を5つご紹介します。

- ユズ(柚子)精油
明るく、親しみやすい柑橘の香り。初めての和精油として多くの方に選ばれています。海外でも人気でオレンジやグレープフルーツと肩を並べる存在。
▶ ユズ精油の商品ページへ - ヒノキ(檜)精油
森の中にいるような深い安らぎと清潔感のある森の香り。空間づくりにもおすすめ。枝葉の香り、木部の香りで印象が変わるので嗅ぎ比べも楽しい。
▶ ヒノキ精油の商品ページへ - 国産ラベンダー(オカムラザキ)精油
濃厚でやわらかな甘さを感じるラベンダー。海外産ラベンダーが苦手でもこれは好き!という方もいます。
▶ 国産ラベンダー精油の商品ページへ - ホウショウ(芳樟)精油
甘さとさわやかさのバランスが素晴らしい香り。気持ちを穏やかに整えたいときに。嗅げば嗅ぐほど癖になります。
▶ ホウショウ精油の商品ページへ - クロモジ(黒文字)精油
ウッディで華やかな甘さがありながら、落ち着いた印象。希少で高価ですが、それにふさわしい気品あふれる香りです。
▶ クロモジ精油の商品ページへ - 上記以外で人気の和精油
ショウガ精油
さわやかでスパイシー!生ショウガをすりおろした時のような香り。寒い季節や冷えが気になるときにおすすめです。
コウヤマキ精油
若葉をちぎった時のような緑の香り。「心のデトックス」を助けるような静けさがあり、人気が高まっています。
イヨカン精油
ユズとはまた違う、甘みのある明るい柑橘の香り。ほっこりしたいとき、前向きな気分に切り替えたいときにぴったり。
ヒバ精油
抗菌・防虫作用で知られる精油。温かみのある落ち着いた木の香りが特徴的。
和ハッカ精油
すっきりとした清涼感がありながら、どこかやさしい香り。夏の暑さ対策だけでなく、イライラして眠れない夜にも使ってみてほしい香りです。
※香りの感じ方や好みには個人差があります。
香りのやさしさと、暮らしへのなじみやすさ
和精油が「心地いい」と言われる理由のひとつは、その“静けさ”にあるように思います。
ふわっと香って、すっと消えていく。空間に溶けるように広がり、主張しすぎない。
この“穏やかな香り立ち”こそが、国産アロマの魅力でもあります。
たとえば、かおりとで人気のクロモジ精油。
ウッディな香りに少し甘さが重なったような香りで奥深いのに、部屋に香らせても“強すぎる”ということがありません。
日常のなかで自然に息を吸い、吐く、その動作の延長にあるような香りです。

香りが強ければ良いというわけではない。
和精油に触れていると、そんなあたりまえのことを思い出します。
香りが主役になるのではなく、静かに整える。それなのに感情には響く。——そんな香りを求める人が、少しずつ増えているのかもしれません。
日本人の感性に寄り添う「和の香り」
同じ植物から抽出された精油でも、香りは国や地域、そして作り手によって大きく異なることがあります。海外から輸入されて量販されている精油の香りが均一なのは、良くも悪くも「調整」されていることがあるからです。
一方で、国産アロマや和精油 ブランドの多くは、その土地の風や土、季節の湿度までもが香りに映り込みます。
自然そのものの個性を大切にしているからこそ、ひとつとして同じ香りがありません。
精油の原料となる植物が育つ気候や土壌が違うのはもちろんですが、もうひとつ見逃せないのが、「どんな香りを抽出したいか」という、作り手の思いです。
良い香りを丁寧に引き出そうとするのか。
それとも、できるだけ多くの量を採ろうとするのか。
その“姿勢”が、香りの印象にまで影響する——そんな世界が、精油にはあります。
日本で作られる精油には、「たくさん採ることより、良い香りを採りたい」という思いが反映されて人気が出ているように感じます。
それは、職人気質ともいえるし、小規模生産という背景から来る選択かもしれません。
実際に、私たちは産地を訪れて、生産者さんと話をするなかで、その一滴一滴に向けるまなざしの丁寧さに、何度も心を打たれてきました。

香りには、文化や感性が映ります。
そして、その文化や感性を“香りの中に宿らせよう”とするのです。
このような背景を知ることが、「和精油の選び方」のひとつの鍵にもなります。
つまり、香りを選ぶことは「誰が、どんな想いでつくった香りを選ぶか」ということ。
それが、和精油のブランドを選ぶうえで大切にしたい視点です。
国産だからこその安心と信頼
かおりとの精油は、すべて100%国産です。
原料となる植物も、国内の畑や山から。クロモジやヒノキなどの日本の固有種はもちろん、ラベンダーやティーツリーのように外来種であっても、日本で種から育てられたものを使っています。
なぜ、そこまで産地や育て方にこだわるのか。
それは、香りが「どこで」「どう育ち」「誰が」「どんな思いで」抽出されたかによって、まったく別物になると知っているからです。
さらに私たちは、第三者機関による精油の成分分析を行っています。
それは、有害な成分が含まれていないこと(=安全の一つの要素)を証明するとともに、その精油の個性を確認するためです。
精油はよい香りで人気になることもありますが、セラピーとしてそれを使う時には、どんな成分がメインになっているかという情報が大切だと考えています。感覚的な香りの情報と併せて、成分からも精油をひも解くことができれば、もっと、日本の精油の魅力が見えてくると思うのです。
実際に、アロマを勉強された方やセラピストの方から、「ここは信頼できる」と選ばれることが増えました。
そうやって“香りを選ぶ目”を持った方が使い始めたことで、和精油は少しずつ、でも着実に広がりを見せているのだと思います。
“自分だけ”の香りに出会えた、特別な感覚
香りを選ぶとき、「なんとなく好き」「なぜか落ち着く」という感覚で選ぶ方も多いのではないでしょうか。
でも実はその“なんとなく”の中に、自分の感性や気質と響き合う何かがあるのだと思います。
あるとき、青森ヒバの香りを嗅いだお客様が、「この香りを嗅いだら、涙が出そうになった」と言われたことがありました。
香りが記憶に触れたのか、それとも、その方の奥にあった疲れや緊張が緩んだのか。
よくよくお話を伺うと、大好きだったおじいちゃんが製材所をしていて、遊びに行った時の匂いと同じだったそうです。子どものころのおじいちゃんとの思い出や懐かしさ、それと同時にさまざまな感情が湧き起こったのでしょう。

香りは、自分とつながるためのツールにもなります。
情報でも理屈でもなく、感覚で選び、感覚で受け取る。
そんな“感覚の居場所”のような存在を見つけたとき、人はその香りに「自分らしさ」を感じるのかもしれません。
ナチュラルでシンプルに暮らす|和精油がなじむライフスタイル
ここ数年、「なるべく自然なものを選びたい」「必要なものだけで、丁寧に暮らしたい」と考える方が増えたように感じます。
私たち自身も、そうした感覚に強く共感しています。
国産アロマや【かおりと】のような和精油のブランドは、そんな想いに寄り添う存在です。
和精油は、暮らしの中に自然と溶け込み、心地よい距離感で香ります。
香水のようにまとわりつく香りではなく、ふとした瞬間に気持ちを整えてくれるような“静かな香り”。
誰かに見せるためではなく、自分のために香らせる。
そんな使い方ができるのも、和精油の魅力であり、人気の理由です。
和精油の使い方はとてもシンプル。
ディフューザーで香らせたり、エタノールを使ってアロマスプレーを作ったり、コメヌカ油やツバキ油にブレンドしてボディケアに使うのもおすすめです。
生活の中で香りを“飾る”のではなく、“なじませる”。それが和精油の本質です。
また、香りを選ぶときは「どんな香りが心にしっくりくるか」を軸にするのがポイント。
和精油を選ぶポイントは、香りの強さや系統よりも「心地よさ」や「使う場面」を重視すると、自分に合った香りに出会えます。
丁寧すぎる暮らしも、ストイックな自然志向も必要ありません。
ただ、自分の感覚に「これが心地いい」と思える香りがそばにあること。
それだけで、日常が少しやさしくなる気がします。
あなたも、「和精油を使う人」のひとりに
和精油の魅力は、単に“日本のもの”だからではありません。
香りの中に込められた、作り手の想い。文化や風土。
そして、それを受け取る私たちの感性が、自然とそれに気づいているからこそ、選ばれているのだと思います。
国産アロマや和精油は、香りを通して日本の自然とつながるための小さな扉のような存在です。
毎日の暮らしの中で使うことで、四季のうつろいを感じたり、心を落ち着けたり。
「自分を整える時間」を生み出してくれるのも、和精油の魅力のひとつです。
もし「和精油を使ってみたいけれど、何から始めたらいいかわからない」と感じているなら、
かおりとのウェブショップでは、香りごとに特徴や使い方を紹介しています。
暮らしに合う一本を、ぜひ見つけてみてください。