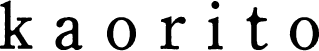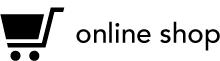小さな約束から始まった想い
「この香りを、流行で終わらせるつもりなら、取材は断ります」
そう言われたのは、まだブランドを立ち上げる前、日本の精油の産地を訪ねていた頃のことです。
その言葉の重みは、今もずっと心に残っています。
私は、日本の精油の歴史を調べる中で、その土地にたどり着きました。
そこで出会った生産者に、単なるブームとしてではなく、海外のアロマではなく日本の精油を使うことが自然になる世の中にしたいという想いを伝えました。

あれから10年近くが経ちます。
そのとき交わした小さな約束は、少しでも果たせているだろうか――。
そう思い返すことがあります。
そして今も変わらず感じているのは、日本の精油が日々の暮らしに根づく文化として育ってほしいという願いです。
その想いを、これからも「かおりと」を通じて伝えていきたいと考えています。
- 和精油とは──日本の香りの定義
- 日本の精油が、私たちにしっくりなじむ理由
- 香りをつかうことが、文化を育てることになる
- 香りが日々の暮らしに根づくこと
- 本物の香りを、自分の感覚で選ぶということ
- 関連ページのご案内
和精油とは──日本の香りの定義
「和精油」という言葉が、少しずつ広まりつつあります。
でも、その意味が曖昧なまま使われている場面も多く見かけます。
かおりとでは、次のように考えています。
- 和精油:江戸時代より前から日本に自生している植物(日本固有種)から採れる精油
- 日本産精油:ローズマリーやラベンダーなど、外来種を日本国内で栽培・抽出した精油
どちらも「国産」であることに違いはありません。
けれども、その背景には植物が持つ文化的なつながりや記憶の根のようなものが宿っています。
和精油には、日本の風土の中で育ち、長い時間をかけて人の暮らしとともにあった香りがあります。
その言葉の裏にある背景や、植物が育ってきた土地の空気を、香りから感じ取ってもらえたらうれしいなと思います。
和精油という名前は、単なる分類ではなく、香りの奥にある時間や文化を伝える手がかりでもあるのです。
日本の精油が、私たちにしっくりなじむ理由
和精油の香りに触れて、
「なんだか懐かしい」「昔の記憶がよみがえった」
という声をいただくことがあります。
それは偶然ではありません。
たとえば、ヒノキの香りには、木造校舎や温泉旅館のような場所の記憶が重なります。
クロモジの香りには、静かな山道や苔むした林の空気を思い出す人もいます。
香りは、記憶や感情と強く結びついている感覚です。
だからこそ、その土地で育った植物の香りが、その土地の暮らしにしっくりくるのです。
それは効能ではなく、感覚。
機能ではなく、感情。
それこそが、和精油が持つ“本質的な価値”だと私たちは感じています。
香りをつかうことが、文化を育てることになる
文化という言葉は、何か特別なもののように感じられるかもしれません。
けれど、暮らしの中で自然に使われ、受け継がれていくものこそが、本当の文化なのではないかと私たちは思います。

精油も、同じです。
特別な時に使うのではなく、気分を整えたい日や、ひと息つきたいときに、自然と手に取るもの。
そうして香りが日常に根づいていくことで、日本の植物の香りが、日本の文化として残っていく道が開けていくのだと思います。
そして、使い続けることで、自分の中にその香りの記憶が育っていく。
それは、私たち一人ひとりの中に文化を宿すということでもあるのかもしれません。
香りが、日々の暮らしに根づくこと
「日本のものを海外に届けたい」
その想いを否定するつもりはありません。
けれど、文化・伝統として香りを育てていくには、まずその土地で“当たり前に使われる存在”であることが大切だと思うのです。
私たちは、海外の香りを自然と取り入れるようになりました。それは、それが現地で文化・伝統として根付いていたからに違いありません。
けれども、日本で育った香りが、日本の暮らしの中であたりまえに使われている場面は、まだまだ少ないように感じます。
香りは、特別なものではなくていい。
毎日の中で使われ、選ばれ続けることで、その香りは文化・伝統として根づいていくと信じています。
本物の香りを、自分の感覚で選ぶということ
「和精油が気になる」
「でもどれを選べばいいのかわからない」
そんな声を聞くこともあります。
答えは、きっととてもシンプルです。
自分がいいと思える香りを、感覚で選べばいい。
流行はなく、その香りが自分に必要だと感じるかどうか。
それが、続けていける香りとの向き合い方だと思います。
そしてその選択が、日本の植物の香りを、文化・伝統してつなぐ第一歩になると信じています。