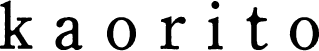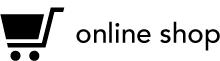目次
ローズマリーの香りはひとつじゃない
花の色で香りが変わる?品種の奥深さ
ローズマリー(学名:Salvia rosmarinus)は、以前は「Rosmarinus officinalis」という名前で知られていましたが、近年の植物分類の見直しにより、サルビア属の一種として再分類されました。植物の研究が進むことで、香りの世界もまた、少しずつ広がりを見せています。

ローズマリーにはさまざまな品種があり、料理に向くもの、精油に向くものと、香りの個性もさまざま。花の色が白、紫、青と異なることで香りの印象も変わると言われており、すっきりとしたものから、ほんのり甘みのあるやわらかな香りまで、バリエーション豊かです。
シソ科の植物は、自然交配や環境による変異が起こりやすい傾向があるため、同じ「ローズマリー」でも育つ土地や株によって香りの印象に違いが出ることもあります。植物の個性に寄り添いながら、どんな香りが現れるのかを楽しむことも、ローズマリーの魅力のひとつです。
日本でのローズマリーの歩み
「迷迭香(めいてつこう)」と「マンネンロウ」
ローズマリーは古代ギリシャ・ローマ時代から親しまれていたハーブで、「記憶」や「献身」の象徴とされてきました。中世ヨーロッパでは宗教儀式や薬草として使われ、人々の暮らしと深く結びついていた存在です。

日本にこのハーブが伝わったのは、明治時代以降と考えられています。西洋文化の導入とともに、観賞用や庭木として紹介され、やがて日本でも、ハーブティーやアロマテラピーの素材として親しまれるようになりました。
その際、中国を経由して伝わった呼び名が「迷迭香(めいてつこう)」。“香りに導かれる”というような意味合いを持ち、東洋らしい詩的な美しさを感じさせてくれます。
また、日本語では「マンネンロウ(万年朗・万年露)」という呼び名もあり、常緑で生命力のあるこの植物に「長寿」や「永続」の願いを込めたネーミングとして伝えられています。
かおりとならではのこだわり
香りのやさしさは、育て方と蒸留の手仕事から
ローズマリーの精油をつくるためには、植物の特性を深く理解し、収穫のタイミングや蒸留方法を細やかに見極める必要があります。
かおりとでは、香りの質を第一に考えた品種選定と、試験蒸留の繰り返しによって生まれた、本当に「ここちよい」と感じた精油をラインナップしています。
この香りを実際に体験してみたい方は、国産ローズマリー精油の商品ページもぜひご覧ください。
香りの奥にある、成分の小さな世界
かおりとのローズマリー精油には、自然由来の香り成分が数多く含まれています。
その中でも特に香りの印象を形づくる3つの成分について、少しだけご紹介します。
α-ピネン
森林を歩くときに感じるような、清々しくウッディな香りを持つ成分です。ヒノキやモミなどの針葉樹にも多く含まれており、日本の「森林浴」の研究でも注目されてきました。
1,8-シネオール
ユーカリやラヴィンサラなどにも多く含まれる、清涼感のあるシャープな香り成分です。ローズマリー特有のハーバルな香りの中核をなす存在でもあります。
ベルベノン
ローズマリーの中でも、特定の品種にしか含まれない希少な成分として知られているベルベノン。香りはどこかグリーンでやわらかく、ほのかに甘さを感じるトーンを持っています。
※この成分紹介は、香りの個性をお伝えするためのものであり、精油の効果効能を示すものではありません。

香りの裏側にある、ていねいな手仕事を感じて
かおりとのローズマリー精油は、「クセがなくて、すっとなじむ香り」が特長。
けれどそれは、偶然生まれたものではなく、品種や収穫、蒸留にいたるまでのていねいな積み重ねの賜物です。
植物の力を信じ、自然と向き合いながら、香りを届ける。
そんな想いが詰まったローズマリーの香りを、あなたの毎日に少しだけ添えてみませんか?
「呼吸が浅くなって、仕事が煮詰まってきたときに選ぶ香りです」
ローズマリーの香りは“頭脳明晰”といわれることもありますが、かおりとの国産ローズマリー精油には、すっきりするだけではないやわらかさがあります。
煮詰まった頭やイライラした気持ちをほぐして、新たな気持ちで仕事に向かえるような、そんな香りだと感じています。
ユズや杉の葉の精油とブレンドして、目覚めの時間や、気分をリセットしたいタイミングにもよく使っています。